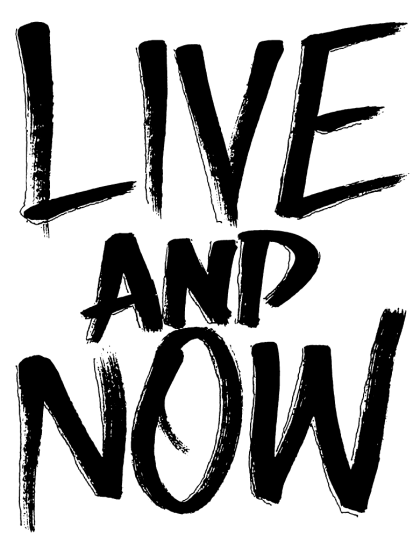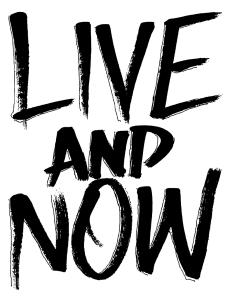この『The BONEZ / LIVE AND NOW』は、去る4月に実施された『We are The BONEZ Tour 2021』の全行程に密着しながら制作された映像作品である。わずか全7公演というこのツアーは彼らの慣例からすればごく短いものであり、通常の状況下で普通に実施されていたなら特筆すべき要素のないものになっていたかもしれない。が、言うまでもなく、その状況自体が当たり前のものではなかったわけである。
2020年に最初の緊急事態宣言が発令された瞬間から、まさかこんなにも長きにわたりパンデミックが続き、「コロナ禍」という目新しかったはずの言葉が定着してしまうことになるとは、地球上の誰も想定していなかったに違いない。誰もが「これ以上悪くなるはずがない」と信じながら従来通りの日常が戻って来ると考えていたことだろう。しかし実際、更新されるのは良くない傾向を示す数値ばかり。そこでいつしか多くの人たちは、かつてと同じ自由を求めることを諦めざるを得なくなっていった。ステージに立つ者たちにとってもそれは同じだ。が、そこで彼らが考えたのは「The BONEZだったらどうするか? 」ということだった。ツアーを終えたばかりの4月末、JESSEは次のように語っている。

“今までのライヴを超えるために、本気でてめえを奮い立たせないと”
「正直に言うと、当初は『今までを超えるライヴができないのに俺らはツアーに挑むのか? 今までの絶頂を感じられないのも承知の上でやるのか? 』と疑問に思ってた。だけど実際にツアーを始めたところで『それはてめえ次第だろ? 』ってことに気付かされた。初日の横浜公演はホントに久しぶりというのもあったから、何がどうあれ聴いてくれる人がいるだけで感無量みたいな感じだったけど、その次の仙台からは『あれ? これは本気でてめえを奮い立たせないと自分が冷めちゃい兼ねないな』という怖さを感じたんだ」
この映像作品の中でも彼自身が語っていることだが、さまざまな制約が伴うこの状況下において、彼らはThe BONEZとしてごく当たり前のライヴを全力で重ねてきた。本来ならば人で埋め尽くされてぐちゃぐちゃになっているはずのフロアに整然と座席が並べられ、その場で立ち上がることは許されてもステージ前に押し寄せることができない観衆は、常時マスク着用を強いられ、声を上げたり一緒に歌ったりする自由を奪われた状態。それを踏まえながら、たとえばライヴ自体のあり方を変えたり、扇動的な言葉を発することを控えたりするというのも、環境への順応という意味においてはきっと正しい選択なのだろう。もちろん彼らにもそうした方法論をとることは可能だった。が、そこで彼らは自らに問うたのだ。「The BONEZだったらどうするか? 」と。そして結果、彼ら自身が考えるThe BONEZ然としたライヴを100%の形で提供することを選ぶことになった。いや、窮屈で不自由な思いをしているオーディエンスに100%のものを届けるために、それ以上のエネルギーを放出することを厭わなかった、と言うべきかもしれない。

“これまで以上に、バンドを観てもらえているという実感があった”
そうしたツアーを経てきたメンバーたちが異口同音に認めているのは、The BONEZが求めてきた自由は、いくつかの行動が制限された程度で失われてしまうものではない、ということだ。ZAXの「これまで以上に、音楽を聴いて、バンドを観てもらえているという実感があった」、T$UYO$HIの「本当に客席からの“気”というものを感じたし、不思議なことに、この状態のほうがむしろ“面と向かっている感”が強い」という言葉は、まさしくそれ象徴している。サポート・ギタリストのKOKIに至っては「聴こえるはずのないものが聴こえてきた」とまで言う。コール&レスポンスが物理的に成立しない環境であるはずなのに、オーディエンスが重ねる声が伝わってきたのだ、と。

“1969年のウッドストック。誰もがその人なりに音を感じまくってる風景”
JESSEはこのツアー中、客席に向けて語りかける際に、1969年に開催された『ウッドストック』のことを幾度か引き合いに出していた。ラヴ&ピースという言葉とともに語られることも多いこの歴史的フェスを、70年代以降のロック・ミュージックの起点、ロックが自我を持ち始めた瞬間などと形容する向きも多いが、その開催時には生まれてもいなかったJESSEがその記録映像などから嗅ぎ取ったのは、半世紀以上前の世界におけるライヴ・ミュージックの楽しみ方の自由度の高さだった。彼は、次のように説明している。
「あのフェスの映像を見てみても、出演者の大半は当時の音楽ファンだって知らないような人たち。全員でシンガロングできるような曲もなければ、モッシュやダイヴ、クラウドサーフみたいなものもない。俺が知ってるライヴ会場の盛り上がり方とはまったく違うものだった。だけど、デカい音で音楽を聴きながら、空を見上げて涙流してるやつがいたり、好きな人と裸でひとつのサンドイッチを食べてたり、そうやって誰もがその人なりに音を感じまくってる風景というのにめちゃくちゃ感動して。今、この状況下で『楽しむ自由を奪われた! 』とか言いたくなる気持ちもわかるけど、実は100個ある楽しみ方のうち3つか4つが規制されただけのことでしかないんじゃないかな。このツアーに来てくれてたお客さんは、きっとそこに気付いたはずだと思う」

“The BONEZとしてのレベルミュージック”
ただ、もちろん、ひとつでも奪われたものがあるなら、それを取り返そう、それ以上に強力なものを手に入れようとするのがThe BONEZのやり方である。JESSEは「俺は、あくまでレベル・ミュージックをやってるつもりでいるから」とも発言している。「元々、何かに歯向かっていきたいからこそこの音楽をやってるわけで。そういう気持ちもないまま、ただただ社会の犬になるんで構わないんだったら、俺は普通にどこかの企業に就職するような道を選んでただろうし」と。
レベル(rebel)というのは単なる反抗や意味のない無闇な抵抗ではなく、納得できない何かに抗いながら自分たちのやり方を貫こうとすることなのだと思う。言い換えれば「The BONEZだったらどうするか? 」という思考に忠実であろうとすること。それは、社会との折り合いをつけながら妥協点をみつけていこうとすることとは違うのだ。
“異常事態の中、ツアー全公演を完遂”
そんな姿勢を貫こうとする彼らを見ていると、相変わらず不器用だな、と感じさせられるところも確かにある。このツアーについても、ある意味、日程のマジックに救われたような部分があった。緊急事態宣言解除と発令の狭間で少しでも公演スケジュールがズレていたら、予定通り全公演を完遂することはできなかった可能性が高いのだ。ただ、そうならずに済んだのは彼らが強運の持ち主だからではなく、さまざまな規制を遵守しながらも、精神的な次元においてそれに抗おうとする姿勢を崩さずにいたからではないだろうか。
自分たちの事情で活動を停止せざるを得なかった時期を経ながら、パンデミックという異常事態により従来通りの自由が得られない状況を「The BONEZだったらどうするか? 」と自問しながら進み続けてきた彼ら。まだまだ不確かな状況は続いているが、今、彼らからの「BONERだったらどうするか? 」という問い掛けに、あなたは明快に即答することができるだろうか? その答えを導き出すヒントが、この映像作品には詰め込まれている。
増田勇一